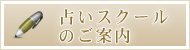二十万人という被害者数の信憑性であるが、漢の高祖劉邦が項羽を論難した10項目のうち6番目にある数字であり、当時は誰でも知っていたことがわかる。
「史記」の原文は次の通り
「詐(いつわ)りて秦の子弟を新安に阬(あな)にすること二十万、其(そ)の将を王とす。罪六なり」
高野白山訳
「新安では秦の若者をだましうちにして、二十万人も阬(あな)にして、将だけをを王に取り立てた。これが罪の第六である」
垓下の戦いで滅亡を覚悟した項羽の心境は次の通りである。
垓下の歌
「力は山を抜き 気は世を蓋ふ 時に利あらずして 騅(すい)逝かず 騅、逝かざるを 奈何(いかん)せん
虞や虞や 若(なんぢ)を奈何(いかん)せん」
項羽は、敗北の原因は、自分ではなく、時勢にあると、思っていたのである。
これに司馬遷は「史記」で以下のように激しく批判している。
史記:
「みずから攻伐に矜(ほこり)り、其の私智を奮いて、古(いにしえ)を師とせず、覇王の業と謂(おも)い、力征を以って、天下を経営せんと欲せしも、五年にして卒(つい)に其の国を滅ぼし、身は東城に死せり。尚お覚寤(かくご)せずして、みずから責めざしは、過てり。乃ち〚天、我を滅ぼす。兵を用うるの罪にあらざるなり〛を引く。豈(あ)に謬(あやま)らずや。」
高野白山訳
「自分の功業を誇り、浅知恵ばかりに頼って、過去に学ぶこともせず、ただ覇道のみを信じ込み、武力で天下を経営しようとしたが、五年間でついにその国を失ったのである。東城で死んだときでさえ、そのことに気が付かず、みずからを責める気持ちがなかったが、それは間違っている。しかも『天がわたしを滅ぼすのだ。戦術のまずさではない』と言い張るに及んでは、むちゃくちゃではないか」