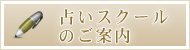七赤金星生まれの人(令和6年2月4日から令和7年2月3日までの一年間の運勢)
○運勢~離合集散運
・七赤金星が離合集散運を意味する、火炎、華麗、離合集散、露見の離宮(りきゅう)に入ります。離宮は、季節は真夏、方角は南、一日のうちでは真昼を表します。
・離宮は、陰が陽と入れ替わる位置なので、表面的には華やかですが、心理上は、むなしさを感じ続けることが多々あるでしょう。
・炎のような明るさに満ちた年なので、地味な努力が評価されることもあれば、逆に秘密にしておきたいことがあらわになったり、善いことも悪いことも表面化し、万事はっきりと明白になります。
○生活の指針
・華やかな雰囲気に包まれて交際も派手になり、称賛されることも多くなりそうですが、有頂天にならず、隠し事が露見してもあらかじめ心の準備をしておいて、外部には動揺を見せてはいけません。
また、新しい人間関係ができたと思ったら、長年の友人や彼氏・彼女と離れるという離合集散の年になりそうです。
・職場では、昇進、栄転、表彰という暗示がありますが、出る杭は打たれる、というように足を引っ張られることがあるので、同僚、取引先の動向に注意を怠ってはいけません。スタンドプレーが目立ち過ぎてかえって悪評を立てられないよう注意して下さい。
・商売・事業では、斬新な発想で、優れた企画書を提出するなど好調が期待できますが、コスト管理を怠り、内情が苦しくなる可能性があります。文書ミスや見積違いなど契約上の問題が出てくることがありますので、契約書案を再読して下さい。
・恋愛は、熱しやすく冷めやすく出会いと別離の年になりそうです。交際相手のいない人は、いつもより華やかな雰囲気に包まれるため、新たな出会いが期待できます。恋愛中の人は情熱が激しく刺激されるため、愛情の深化が仇となって、相手を束縛する気持ちが原因で別れの暗示があります。
・家庭生活も万事派手になり、高価な買い物や浪費をする傾向が出てくるので、無駄使いをさけて下さい。離合集散の時でもあるので、転勤や独立で家族の構成メンバーが変わる可能性があります。そろって家族旅行を楽しむなど連帯感を密にして下さい。
また、今年は火を意味する星廻りになるので、たばこやストーブによる火事に注意する必要があります。
・もともとコツコツと貯蓄するタイプですが、今年は、衝動買いや派手な付き合いが多くなり、内実が苦しくなるので、見栄をはらないよう心がけて下さい。
○基本的運命
・七赤金星の人は、陽性で派手、お洒落で流行の先端を追いかけたがり、また人を惹きつける不思議な魅力を持っています
・臨機応変で商才にたけているのが普通で、金運が強いものの、人一倍浪費癖があるので、貯蓄は苦手なタイプが多いでしょう。
・この星に生まれた人は、同じ過ちを何回も繰り返すのが特徴です。失敗の理由や原因をとことん追求し、把握する癖をつけ、今後に生かしていくという姿勢を持ちましょう。
八白土星生まれの人(令和6年2月4日から令和7年2月3日までの一年間の運勢)
○運勢~低迷忍耐運
・八白土星が低迷忍耐運を意味する、水流、陥没、困難、創作の坎宮(かんきゅう)に重なります。坎宮は、季節は真冬、方角では北、一日のうちでは真夜中を意味します。
・一つの問題が解決しても、行き違いや当て外れがあり、落とし穴が連続するように新たな悩みや課題が次々と出てきて、意気消沈することが多いかもしれません。
・しかしながら、あわてず、あせらず、洪水が引くのを待つつもりであれば、逆にこの一年間は、パワー充実、来年に向けて実力をつけるチャンス到来の年となります。
○生活の指針
・休日は、30分か1時間だけ早起きして趣味やスポーツどんなことでもかまいませんので、自分のしたいことや適性に合うことを見つけて、トレーニングの時間にあてて下さい。
・運気は最低ラインで停滞しますが、来年以降の運勢を決定づける今年は、創作活動や勉強・研究が進捗する年でもありますので、この時を活用して、資格取得試験に挑んだり、稽古ごとの練習を始めるといいでしょう。
・悩みは、一人で抱え込まずに信頼できる人に相談し、解決へのヒント、道筋を立てるよう心がけて下さい。
・職場では、自分の手に負えないような、無理な仕事にとりかかると痛手が大きくなりますので、事前に上司、先輩に相談する必要があります。新規業務は何回も見直して検討した上で取り組んで下さい。運勢が弱い時なので、今年は、転職、異動、独立は見合わせた方がいいでしょう。
・商売・事業では、内部対立や企画不備で見込み違いが起こりやすいので、投資は控え、経費削減に努め、現状維持を目標とするのが賢明でしょう。ただし、計画立案するには良い時期です。
・今年は、感情に流され、刹那的な行動をとりやすく、物事が破れやすいので、秘密の交際や不倫などは飛躍の妨げになり用心する必要があります。
・多事多難な今年は、イライラを家庭に持ち込んで口論となることがありますので、すきま風が吹かないよう、家族への思いやりと会話を増やすことが大切です。
・貯蓄が得意で生れつき金銭運にめぐまれているものの、今年は不調で収入は増えませんので、節約を心がける必要がありそうです。不動産取引や株式をはじめとする投資は、持ち出しになるでしょう。
・今年は身体が冷えやすくなったり、病気にかかりやすくなるという暗示がありますので休養、食事、医療といった健康管理を怠らないようにしましょう。
○基本的運命
・八白土星の人は、信仰心が強い上、カンが鋭く、ギャンブル運も強く、人当たりは柔らかですが、実は自分の生き方に反することを強要されると、てこでも動かなくなる頑固さが出てきます。
・頑固を押し通すと、サラリーマンであれば組織の一員として立場を守れなくなり、つま弾きされてしまうことがあります。
・就職は、まず自分のしたいことを見つけ出して好きな方向、職種に進むという手順を踏む必要があります。会社を選ぶというより、適性のある仕事を選ぶ必要があります。
九紫火星生まれの人(令和6年2月4日から令和7年2月3日までの一年間の運勢)
○運勢~準備立命運
・九紫火星が準備立命運を意味する、母、従順、根気、労働の坤宮(こんきゅう)に回り込みます。
・今年は、衰退の運気から逃れるので、大地に足が着いたようにほっと安心できる年になり、未来へ向けて蒔いた種子がいよいよ発芽の準備をはじめるでしょう。
・昨年の不調を引きずる今年前半に課題に取り組むと、後半から少しづつ活力増進の気運が出てくるので、解決へ向けて事態が動き始めます。
○生活の指針
・人の意見を参考にしたり、従順に教えを乞う姿勢、また信頼できる友人に相談する気持ち、そして人づきあいをよくすれば、穏やかに平和に生活することができます。
・真面目に努力を続ければ評価されますので、当面独立独歩を考えずに、一歩退いた立場で、地道に女房役、裏方に徹することが成功への近道です。
・職場では縁の下の力持ち、見栄えがしない、損な仕事が回ってきてもくさらずやり遂げることが大切です。働く意欲が湧いてくるので、万一転職が避けられない場合は、今の仕事を続けながら、根気よく希望する職種を探して下さい。
・商売・事業では、将来の飛躍に向けて、人材育成研修の実施、原価低減をはじめとする経費の削減に努めなければなりません。今年は、不動産の買収、売却に縁がありそうです。
・飲み友達、幼なじみ、職場など身近な所で恋愛のチャンスがあり、結婚相手が見つかる可能性があります。交際中の人も結婚への意識が高まる傾向があります。
・家庭内が明るさを取り戻し、活気が出てきます。運動会やPTAなど学校行事にすすんで参加し、家族を支えるサポーターの一人として意識して会話を増やし、絆と連帯を強めて下さい。
・土地との縁が深くなり不動産売買の暗示があるので、ローン返済の見込みがたち自宅購入の可能性があります。
・生れつきの金銭運に加えて、今年は仕事への意欲が評価されるにつれ、収入も少しずつ増えてきそうですが、気を緩めて無駄使いしないように気をつけなければなりません。コツコツと貯蓄の楽しみを知る時です。
・今年後半から活発に動く日々が始まるので、胃腸の働きを助けるため、暴飲暴食を控え食事の時間を充分に確保して下さい。
○基本的運命
・九紫火星の人は、直観力が鋭く、個性的で派手、独断専行の実行力があるタイプです。自分を売り込むことも上手で、何をしても認められるのが早いので、ツキがある生活を送ります。
・社交性に富み、目立ちたがり屋で、粘りに欠けるものの、予想外の不利な事態でも持ち前のカンの良さで逃げ足が速いため、一生を通じて大失敗することはありません。
・成功をあせりすぎたり、口八丁、手八丁の人気者なので妬みをかったり、また熱しやすく冷めやすい性質なので、人の恨みを買い、足を引っ張られることがあります。