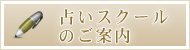さざれ石は、本来小さな石の意味であるが、長い年月をかけて小石の破片が集まって、その隙間を炭酸カルシウムや水酸化鉄が入り込み、一つの大きな岩の塊に変化したものである。
これを石灰岩の一種である石灰質角れき岩という。
「君が代」では、この岩を指して「さざれ石の巌(いわお)となりて」、と永遠の象徴としてうたっているのである。
徒然の記
ブラ高野~さざれ石
立春への疑問 その2
⑴ 閏月(うるうづき)の設置
前述のとおり、太陰暦の1年分は354日(29.5日×12月)なので、地球が太陽の周りを一周する365日に年間で11日足りず、3年で33日分のズレが生じることになる。観測の結果、太陽暦で19年たつと、月と太陽の周期が一致することが判明している。
では、太陽暦の19年は、太陰暦で換算すると、何年になるのだろうか。
太陽暦の19年分は、365.242194日(太陽暦の1年)×19年=6,939.601686日
太陰暦の19年分は、
354.367068日(太陰暦の1年)×19年=6,732.974292日
6,939日から6,732日を引くと、207日になる。
207日を太陰暦の1月分である29.5日で割り戻すと、207日÷29.5日=7.01月→約7月分不足する。
これで太陰暦に換算した場合、19年で7月足りないことがわかる。
太陽暦では4年に1回閏年を置くが、太陰太陽暦では、19年間のうち7月分の閏月を加えて太陽の動きに暦を合わせる、という段取りになるのである。
実例をみると、天保三年(西暦1832年)壬辰暦では、大の月、小の月及び閏月は、11月に閏月として大の月(30日間)を追加しているので、1年間が13か月あり、日数も30日間増えて384日となる。
⑵ 二十四節気(にじゅうしせっき)の導入
閏月の設置により季節のズレを修正するものの、19年かけてズレを予測しては閏月を増やして調整するだけなので、これは誤差が完全に無くなるということではない。
そこで、毎年太陽の動きを読み取った季節情報をカレンダーに書き込んで注意を喚起すればいいわけで、これら季節や気候をあらわす、情感にあふれた詞(ことば)を二十四節気(にじゅうしせっき)という。
毎日太陽の動きを観測して、地球上空の太陽が通る軌道である黄道(こうどう)を記録しておけば、太陽の位置によって暑くなったり寒くなったりする時期がわかるので、季節の到来を予測できるようになるのである。
黄道(こうどう)は円を描いているので、これを360度として24等分し、それぞれに春の始まりを意味する立春や昼と夜の時間が等しい春分と秋分、田植えの時期を知らせる芒種(ぼうしゅ)という名称をつけ、太陰暦に当てはめて季節を知らせれば飛躍的に使いやすくなるのが道理である。
それでも立夏が太陽暦の5月5日頃、立秋が8月7日頃で季節感のズレを生じる場合がある。
そこで、もう一工夫して新たにつくった暦日を雑節という。
二十四節気(にじゅうしせっき)のうち、主な暦注は次の通りである。
なお、日付は太陽暦換算である。
立春(りっしゅん)~暦の上では春(2月4日頃)
啓蟄(けいちつ)~冬ごもりの虫たち目覚める(3月5日頃)
春分(しゅんぶん)~昼夜等しき長さ(3月20日頃)
立夏(りっか)~薫風そよぎ、夏はじまる(5月5日頃)
夏至(げし)~1年で一番昼が長い(6月21日頃)
大暑(たいしょ)~1年で最も暑い頃(7月23日頃)
立秋(りっしゅう)~秋の気配立つ(8月7日頃)
白露(はくろ)~野草に露がつく(9月7日頃)
秋分(しゅうぶん)~昼夜等しき長さ(9月23日頃)
立冬(りっとう)~冬の気配立つ(11月7日頃)
大雪(だいせつ)~真っ白な雪、空も地も覆う(12月7日頃)
冬至(とうじ)~最も日が短い、冬のさなか(12月22日頃)
大寒(だいかん)~1年で一番寒い (1月20日頃)
⑶ 雑節(ざっせつ)による補完
黄河流域で生まれた、直輸入の二十四節気を補助する意味で、日本列島の風土、生活習慣を表す特徴を暦に記入すると、格段に使い勝手が良くなり、梅雨入りを知らせる入梅や嵐の到来を告げる二百十日などがある。これらの名称を雑節といい、日本独自の暦日である。
節分(せつぶん)~立春の前日、季節を分ける日(2月3日頃)
彼岸(ひがん)~先祖へ感謝する日、(春分の日・秋分の日)
社日(しゃにち)~産土神へ感謝する日(3月22日頃、9月18日頃)
八十八夜(はちじゅうはちや)~立春から数えて88日目(5月2日頃)
入梅(にゅうばい)~梅雨入り(6月11日頃)
半夏生(はんげしょう)~梅雨明け(7月2日頃)
土用(どよう)~立春、立夏、立秋、立冬の前日までそれぞれ18日間、
二百十日(にひゃくとうか)~立春から数えて210日目(9月1日頃)
二百二十日(にひゃくはつか)~立春から数えて220日目89月11日頃)
ブラ高野~シロウオ漁
立春への疑問 その1
九星気学による運勢判定の1年間は、立春(ほぼ2月4日)から始まり翌年の2月3日までであるが、立春とはよく聞くものの、春が始まるのになぜ寒いのか、わかったようで明確に説明できない概念である。本資料は、立春の概念を調査した結果報告である。
真冬の真只中なのになぜ立春というのか。太陰暦は、なぜ季節感がずれているのか。
忠臣蔵の討ち入りは、太陰暦で12月14日(西暦1703年)であるが、現在の太陽暦では1月30日となり、300年前とは約1月半のずれがある。
易経の19番目である地澤臨の8月は、太陽暦換算で9月か10月である。
地澤臨では、
「臨は、元いに亨りて貞しきに利ろし。八月に至れば凶有らん」
太陰暦の基礎的な仕組みは次の通りである。
(1) キーワード
太陰とは、月のことをいう。
太陰暦は、月の満ち欠けを基につくられた暦であるが、太陰暦を理解するキーワードは、月の満ち欠けが一巡する29.5日という数字と朔(さく)、望(ぼう)、晦(つごもり)という闇夜や月夜を意味する名称である。
太陰暦では、毎月の初日は全く月が見えず、月の見えないこの状態を朔(さく)といい、
毎月の1日を「朔日」とも呼び、八朔といえば、8月1日のことを指しているが、八朔という夏ミカンの名称は太陰暦に由来しているのである。
快晴の夜でも月が見えない日を毎月の1日と設定するのである。
この時の見えない月をなぜか「新月」というものの、ネオンサインはおろか電灯もない時代は深い闇に包まれたまま真っ暗な長い夜が続いた。
明智光秀が織田信長を討ち取った本能寺の変は、天正10年6月1日(西暦1582年6月20日)の夜であった。この日は太陰暦の1日なので、新月すなわち月がない闇夜であった、暗殺の計画性は歴然としていたのである。
月の運行を見ると、満月になるまで15日間かかるので、満月が出る日を毎月の15日に設定する。
夜空を見上げて、満月が出ていると、この日は、太陰暦でいうと必ず15日になる。
夜は、中天に輝く月が煌々と光を放ち周囲を真昼のように明るくするが、この明るい夜を招く満月の状態を望(ぼう)という。
日本の行方を決定し、世界史にも影響した関ヶ原の戦いー日本年号の慶長5年9月15日(西暦1600年10月21日)の夜は、雨や曇りでなければ、15日なので日本各地で満月が出ていたことがわかる。もっとも関ヶ原周辺は、夕方から雨模様だったようである。
晦(つごもり、かい)は、くらます、わかりにくい、という意味である。
月末(30日か29日)になれば、月は再度見えなくなる。これを晦(つごもり)といいまたは、みそかとも読むが、今でも年の終わり12月の31日を大晦日(おおみそか、おおつごもり)というのは、太陰暦の名残りである。
(2) 太陰太陽暦
太陰暦の1箇月を1朔望月と呼び、1朔望月は約29.5日なので、12朔望月(1年間)は、約354日となる。
そこで太陰暦をつくる場合は、30日ある月(大の月)を6個、29日しかない月(小の月)を6個設けることになる。
そうすると、
30日×6個=180日
29日×6個=174日
180日と174日の合計で、ちょうど354日である。
ところが、月の満ち欠けを基にした太陰暦は、比較的容易に作成でき、月の形さえ見れば日にちの見当がつくという便利な半面、太陽の動きを反映していないので、種まきや収穫の時期がわからず、季節感や生活実感とも違って使い勝手が悪いので、これを補正した暦を太陰太陽暦という。
太陰太陽暦は、太陰暦の一種である。
補正の方法は、三つあって、一つは閏月(うるうづき)の設置、二つ目は二十四節気(にじゅうしせっき)の導入、三つ目は雑節による補完である。
ブラ高野~日本銀行福岡支店
暦の見方 その14 まとめ
1 概要
暦がわかりにくいのは、暦に記載された事項や行事が多すぎるからである。これらは、根拠が不明だったり、凶日がむやみに多い。
さらに新暦と旧暦をごちゃまぜにして暦に記載していることも読みにくい原因である。
迷信にとらわれたり、また拒絶して無関心になったりするのではなく、占い師として正しい知識を習得し、素養の一つとして占いに役立てる姿勢が肝要である。
主な注記を説明しよう。
2 干支(かんし)
十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせた60回を周期とする数字の並びを干支という。これは、年、月、日、時間、方角など特定するために用いられる。
干支を使えば、10と12の最小公倍数である60までの数字を表現できる。
3 九星
方位・運勢・性格・相性を占うために用いる九つの星の総称~一白水星、二黒土星、三碧木星、四緑木星、五黄土星、六白金星、七赤金星、八白土星、九紫火星がある。
4 六輝(ろっき)
六輝とは、先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の総称であり、六曜または六曜星ともいわれている。
5 二十四節気
太陽の軌跡である黄道の1年分を24等分し季節情報を知らせる名称であり、立春をはじめとした、24種類の季節を表現する詞(ことば)である。
6 雑節(ざっせつ)
黄河流域で生まれ、中国から直輸入された二十四節気を補強する日本列島独自の風土、生活習慣に基づいた留意事項である。
節分、彼岸、八十八夜などがある。
7 中段(十二直)
十二直は、北極星を中心に北斗七星の取っ手部分が回転して円軌道を描くので、これを十二区分し、十二支の方位と結び付け名付けした上で吉凶判断に活用したものである。
十二直の直は当たる、という意味があるものの、吉凶の根拠は不明である。
十二直は、暦の中段に書かれているため、単に中段と呼ぶこともある。
8 二十八宿(にじゅうはっしゅく)
古代中国の天文学で季節を知るために用いられた二十八宿は、地球から見た太陽の軌道である黄道を28のエリアに不均等分割し、それぞれを宿(しゅく)と呼び、星座名をつけたものである。
四方に七つの星座を当てはめ、吉凶を書いているものの、吉凶の根拠は不明である。
9 下段~暦の下段に記載されている、大みょうや天おんなどは根拠もなく、迷信の要素が強いため省略
10 庚申(こうしん)
庚申は、六十干支の一つで、57番目である。60日のうち1日は庚申となる。
庚申信仰は、中国伝来の道教をもとに、密教・神道・修験道が混淆(こんこう)し、地元の寄合い制度に組み込まれた土俗習俗である。
庚申の夜は、三尸虫(さんしちゅう)という虫が、眠っている間に天帝という神様に悪事を報告しないよう眠らず徹夜して過ごしていた。
これを庚申待(こうしんまち)という。庚申待を記念した庚申塚が日本各地に建てられている。地域によって庚申待は数百年間続いたが、大正年間まで各地で行われていたことを考えると、日本文化の重層的な陰影の濃さを垣間見ることができる
11 八朔(はっさく)
旧暦の8月1日のこと、新暦の令和4年では8月27日である。
12 選日(せんじつ)
⑴ 概要
暦の注意書き(暦注)のうち、六十干支の組み合わせで吉凶を選んだ日を選日という。
大安、仏滅など六輝、日曜日から始まる一週間の七曜、十二直(中段)、二十八宿、九星、下段以外の総称である。
選日の日々は次の通りである。
・八専(はっせん)
八専(はっせん)は、木と木、火と火など五行の気が重なる、六十干支の49番目から60番目までの凶日(きょうじつ)である。相性判断では、五行が重なる比和は、凶日とはいえない。また五行の気が重ならない相生、相剋の日については間日(まび)という名称で八専(はっせん)の影響は受けない、という。
・不成就日(ふじょうじゅび)
旧暦の各月ごとに8日間に1日の割合で、願いが成就しない日がある、というが、根拠は不明である。
・一粒万倍日(いちりゅうまんばいにち)
一粒のもみが一万倍も実る稲穂になるという意味である。
仕事始め、開店、種まきには吉であるものの、この日に借金すると増えていくという。
・三隣亡(さんりんぼう)
三隣亡は、一説では、当初「三輪宝」と書かれ、「屋立てよし」「蔵立てよし」と注記されていたが、暦の編者が「よ」を「あ」と書き間違え、そのまま「屋立てあし」、「蔵立てあし」と伝わってしまったのではないかという。
「三輪宝」が凶日では都合が悪いということで同音の「三隣亡」に書き改められたのであろう。
三隣亡は、現在とは正反対の吉日だったことになる。
・天一天上(てんいちてんじょう)
人事の吉凶を司る天一神が天に上っている期間。六十干支の30番目の癸巳(みずのとみ)の日から六十干支の45番目である戊申(つちのえさる)の日までの16日間。この間は天一神の祟りがなく、どこへ出かけるにも吉とされた。
・土用(どよう)
⑴ 意味
四季の直前は、大気変化の兆候がでるといわれ、季節の変わり目に体調を整える準備期間であり、これを土用という。土用の期間は原則として18日間である。
土用が明けると春、夏、秋、冬という新しい四季が始まる。
年に4回ある土用は、冬の土用は春に向けて、春の土用は夏に向けて、夏の土用は秋に向
けて、秋の土用は冬に向けて体力、抵抗力をつけるための時間でもある。
⑵ 期間
令和4年の土用は次の通りである。
・冬の土用~1月17日から2月3日まで
・春の土用~4月17日から5月4日まで
・夏の土用~7月20日から8月6日まで
・秋の土用~10月20日から11月6日まで
・十方暮(じっぽうぐれ)
十方暮は六十干支のうち、21番目の甲申(きのえさる)から30番目の癸巳(みずのとみ)までの10日間を相剋(そうこく)の凶日として設定した。根拠は明白であるが、相生(そうしょう)の吉日や比和(ひわ)の日も含まれるので凶日の正当性は薄弱である。
ブラ高野~ビリケンさん
暦の見方 その13 天一天上及び十方暮
・天一天上(てんいちてんじょう)
天一天上は、人事の吉凶を司るという天一神が天に上っている期間で、六十干支の30番目の癸巳(みずのとみ)の日から六十干支の45番目である戊申(つちのえさる)の日までの16日間である。
この間は天一神の祟りがなく、どこへ出かけるにも吉とされた。
・十方暮(じっぽうぐれ)
十方暮は六十干支のうち、21番目の甲申(きのえさる)から30番目の癸巳(みずのとみ)までの10日間を相剋(そうこく)の凶日として設定した。
根拠は明白であるものの、相生(そうしょう)の吉日や比和(ひわ)の日も含まれるので凶日の正当性は薄弱である。
ブラ高野~彫刻「恋人たち」
暦の見方 その12 不成就日及び一粒万倍日
1 不成就日(ふじょうじゅび)
旧暦の各月ごとに8日間に1日の割合で、願いが成就しない日がある、というが、根拠は不明である。
2 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
一粒のもみが一万倍も実る稲穂になるという意味で、一粒万倍日という。
仕事始め、開店、種まきには吉であるものの、この日に借金すると増えていく。